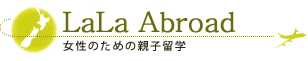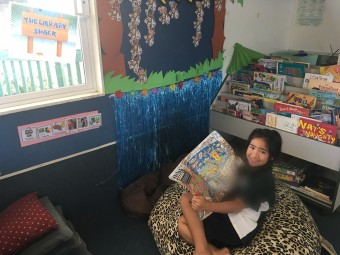先週の記事で、「思春期の子どもの心のコンディション」
に関して書きましたが、今日は小学生のお話です。
娘の小学校では、現在「メディテーション(瞑想)」を取り入れて、
子どもたちの心のコンディションを整えることに力を入れています。
このことを知ったのは、ある日学校終わりの娘に
「今日学校で何したの?」と聞いたら、
「こうやってクラスの全員で床に寝っ転がって死んだ」

と衝撃の返答が![]()
え、死んだ?なんで?遊び?クラス全員?どうして??
もう頭の中は「?????」でいっぱい。
発達障害で、言葉の成長に大きな遅れのある娘なので、言葉で説明するのには
限界があり、同時に「何が起こっているか、何をしているか」も100%理解は
できていないことが多いのです。
質問を重ねれば重ねるほど意味不明が深まり、
「〇〇先生がみんな静かにしてー!って言った」
「先生がテレビをつけた」
「テレビの女の人が怒ってた」
「みんな床に横になって死んだ」
と話が進み、もう何が何だか分からず。
とりあえず生きてることは確かですが![]()
そういうわけで、翌日先生に話を聞くと、
「ああ(爆笑)昨日からメディテーションを全校で取り入れてるの!」
と。(笑)
休み時間が終わった後の5分間、
メディテーションをするためにテレビ(音楽と瞑想を促す音声が流れる)をつけて、
その中で瞑想をリードする女性の声がすごく落ち着いたトーンなので、
我が家の娘には怒っているように聞こえたのでは、ということ。
また、クラス全員がそれぞれ好きな場所で床に仰向けになって、
目をつむってゆっくり呼吸をする状態を、娘は「死んだ」とすごい描写で
教えてくれたということがわかり、一安心。
こうして、5歳児から6年生までが毎日5分、
お腹から深呼吸して、頭の中を一度まっさらにする
ということに取り組んでいます。
周りのキウイの保護者たちと話すと、学校でこういうことをするよりも前から、
もっともっと小さい時から「定期的なメディテーション」をしている子が
驚くほど多く、NZ人たちにとってはかなり日常的なものなのだと知りました。
「身体の健康」はもちろんだけど、
「心の健康」に関しても同じくらい、もしくは身体以上に重要視してくれている
ことが、日常の学校生活からよく分かる出来事です。