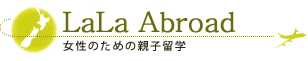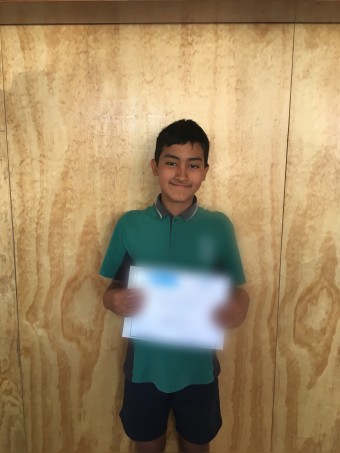今日は新年1つ目の記事ですが、
かなり辛口な(そして自分のことを棚に上げた!)子育て記事です。
先日、オークランドで人気のビーチに行った時のこと。

この日は西オークランドにある、Muriwai Beachというところへ。
波が基本的に高めなので、サーフィンやボディボードをするのに最適です。
ただ、この日は水が相当冷たかったため、ボディボードをしたい子どもたちを
主人に任せて、私はビーチの上でのんびり人間観察したり、ぼーっと考え事をしたり。
そんな時に驚くようなことに気づいてしまいました。
その日、ビーチには何組かのアジア人ファミリーや留学生らしい団体がいました。
ここでいうアジア人とは、日本人・韓国人・中国人のことです。
そのアジア人全員(海の中にいる人は除く)が、携帯電話をいじっていました。
見渡す限り、全員です。

しかもちょっと写真撮ったり、調べ物ををする感じではなく、
ずっとずっと下を向いて携帯をいじっています。
一緒に来た人との会話もありません。
残念ながら、その中に日本人っぽい方々もいらっしゃいました。
一方、キウイはビーチに行く時携帯を持っていかない人も多く、
ビーチで何をしているかというと、お昼寝したり、読書したり。

この写真の目の前の、中・高校生らしきアジア人の団体さんは、
海に背を向けて、3−4時間ずっと携帯をいじっていました。
しっかり予備の充電器も持ってきていて、携帯をいじる準備は万端。
ちなみに、この写真の中のキウイは、少なくとも3人読書にふけっています。
右を見ても、左を見ても、その傾向は同じでした。
このことから改めて思ったのは、
アジア人(私自身を含む)は、空気を読むのは上手くても、TPOをわきまえるのが
あまり上手くありません。格好ひとつとっても、学校のお迎えも、スーパーも、
ビーチのお散歩も、カフェもランチも、シティでのディナーも、基本的に洋服も
バッグも靴もメイクも同じ(改めて言います、私自身を含む)。
いつも基本的にきちんと目にしているのですが、それが行き過ぎだったり、
足りなすぎたりのことが、この国のTPO力が高い人々の中にいると顕著で、
私もよく「しまった、近所のカフェお茶なのに派手すぎた」とか、
「ガールズナイトなのに、お化粧足りなかった」とか、NZ生活10年以上経っても、
まだまだ「しまった!」の連続です。
そんなアジア人の「メリハリのある生活」の下手さが、このビーチでの、
「お日様を楽しまずに、家の中と同じこと(携帯いじり)をしてしまっている」
に凝縮されている気がしました。
キウイの子達もディバイス(携帯やipadなどの電子機器)には相当のめり込みます。
ただ、ビーチなどに行く時は、そもそも親が持たせません。
そして親の携帯を使おうとする子に「今はディバイスの時間じゃないよね?おかしいよね?」
と諭している場面に何度も遭遇したことがあります。
だから、これは「親の教育」なんだと思います。
「ビーチはTPO的にディバイスをするのにふさわしくないところ」というのを、
きちんと教え、親もその姿を見せているんだと思います。
新年始まって間もなく、「人のふり見て我がふり直せ」を実感した、
ビーチでのひとコマでした。
皆さんは、どう思いますか?!