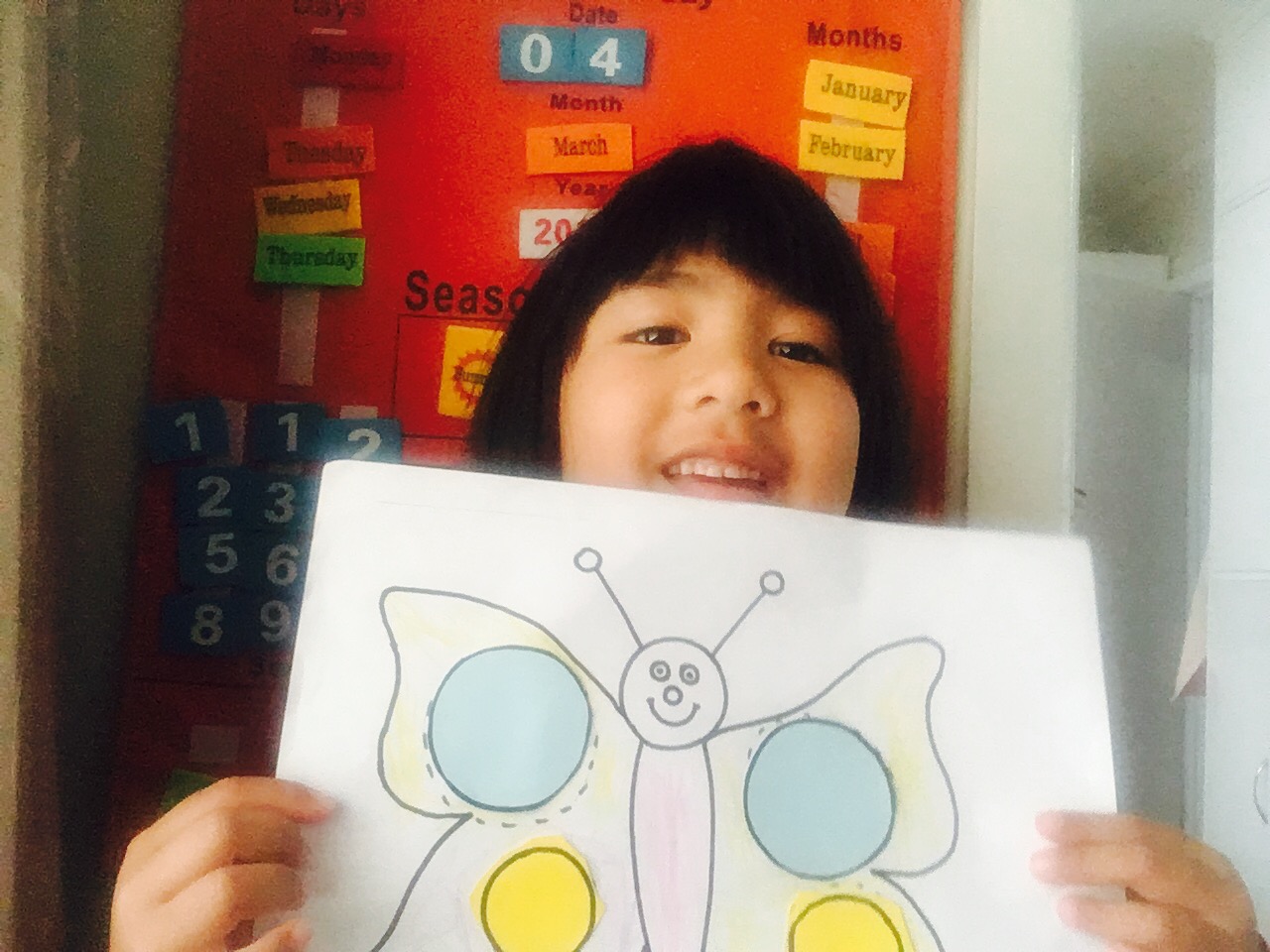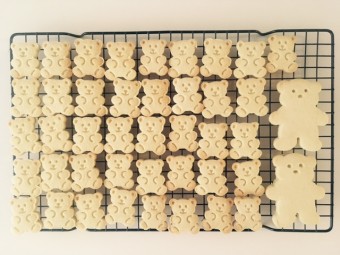新学期が始まり早1ヶ月が過ぎようとしています。
そろそろランチボックスの中身もマンネリ気味・・・
特に今は真夏なので、「痛まない」「子どもが好き」で、
さらに毎日おそとで地べたに座ってピクニックのように食べるので、
「手で持って食べやすい」ものが条件となると、詰めるものも日本とは
ちょっと違ってくるかもしれません。(と先に言い訳 )
)
ここ2週間ほど、子どもたちのランチボックスの中身を写真に撮ったら
「あらやだ、ほぼ同じものばっかり!」に気づき愕然
それでは生活感満載の写真ですが、NZの子はこんなもの食べてます。どうぞ

普通のサンドウィッチですが、私の独りよがりなこだわりとしては、
「台湾系のベーカリーで買った、ほんのり甘い食パン」で作ること
時間がたっても、日本の食パンのように柔らかくて、ほんのり甘くて美味しい

スーパーで買ったチーズパンにツナマヨ&ハムを挟んだサンドウィッチ。
レタス、人参、トマト、チーズは大体どの具のときも入ってます

こっちも丸いパンをスーパーで買って、魚のフライをサンドしました
夏は湖でのヨットの授業などもあるので、運動系が多い日は揚げ物がお約束

あと、こちらの子に人気なのが「ラップサンド」
ソフトタコスのように見えますが、皮はラップサンド専用のもので、
時間が経っても固くならないようにできています。
中に野菜と具をたくさん入れられるのでお気に入り
この日の中身はササミフライ。

ササミフライをソーセージに替えて、ホットドッグ風。

そして、週1〜2の頻度で作っている「巻き寿司」。
この日は前夜の残りの鶏肉を、照り焼きソースに絡めたのが具です。
野菜は、人参・キュウリ・アボカドなどを入れるのが定番!
マフィンは、こちらでも定番になりつつある「米粉」で作りました

四角いお弁当箱にちょうど良い数のお寿司を入れるのが、毎回結構難しい。
日本の100均で買ってきたお醤油入れが大活躍です
右の袋に入っているのはポップコーン!
この日のお寿司の具は、グリルしたチキンと、カニカママヨでした。

この日の具は、冷凍食品のチキンフライ。
冷凍庫に常備しておくと、いざというときサンドウィッチにもお寿司にも
使えるのでとっても便利

我が家の愛用はこのFree rangeシリーズ。
Free rangeチキンというのは、ケージではなく、放し飼いで育てられた鶏ということ。
そして疲れている朝は・・・

冷凍してあるピザ生地に具を乗せて焼いただけの手抜きデイだというのに、
結局子どもたちにはこれが一番喜ばれるという皮肉・・・
こちらの学校でまずびっくりしたのが、「休み時間ごとになにか食べる」ということ
例えば我が家の子どもたちが行く学校は、
1時間目:8:50〜9:55
Brain food:5分休憩=果物を食べる時間
2時間目:10:00〜11:00
Morning tea:30分休憩=朝のおやつの時間
3時間目:11:30〜12:45
Lunch time:45分休憩=ランチの時間
4時間目:13:30〜14:50
となってます。
それぞれの授業の区切りの時間も均等ではないし、日本人からすると
なんとも不思議な感じ
なので、ランチボックスには「Brain food=フルーツ」、「Morning tea=おやつ」、
「Lunch=お昼ごはん」を詰めていかなくてはいけないんです。
子どもたちにとっては、食べてばっかりの幸せな休み時間。
でも朝の親にとってはけーっこう頭を悩ませるものなんです






![]()










 (母は覚悟しなきゃな。笑)
(母は覚悟しなきゃな。笑)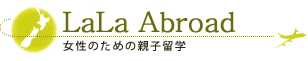








 宿題も、もう週ごとではなく月単位で出て、「取り組むスケジューリング」
宿題も、もう週ごとではなく月単位で出て、「取り組むスケジューリング」